〜「御用聞き」で見上げた豪邸に明日の自分を重ねた〜
「集団就職」とは、昭和史の中のある時代を象徴する“歴史的語彙”で、もはや「死語」といってもいいだろう。 戦 後まもなくより、高度経済成長期にかけて全国各地から都市へと、中学卒、高校卒の若者たちが就職のため集団で移動する姿を指した言葉 だ。とくに東北地方から首都圏を目指すために特別に編成された専用の「集団就職列車」は有名だった。中でも年度替わりの春先に、おびただしい若者が乗った列車が到着する上野駅の光景は風物詩としてもよく知られていた。 基本的には農家の次男、三男など 農業で生活が成り立たない層が、都市部でなかなか労働力を確保できない中小企業に就職する、という姿が一般的だった。大学への進学率が1割程度で、中学卒で就職することがごく当たり前だった当時、地方からやって来て、町工場や商店で働く若い労働者がたくさん存在したのだ。彼ら彼女らこそ、50年代から始まった日本の経済成長を現場で支えた人たちと言えよう。
実は大城もそうした若者たちの1明日の自分を重ねた人だった。そして彼が担った仕事も、いまや「死語」と化し た「御用聞き」だった。
名古屋で「御用聞き」に従事
大城は那覇商業高校を卒業した1960年、集団就職の一員として名古屋へ渡った。本当は東京へ行きたかったのだが、諸事情から名古屋の酒販店で働くことになった。そこで課せられたのは、店の商圏内の家庭を一軒一軒歩いて購入希望商品を(文字どおり)聞いて回って注文を取るしことーーつまり御用聞だった。そのルーツは江戸時代に”お上”から十手を預かり、犯人の捜査や捕縛に当たった目明し・岡っ引きにあるとされるが、いまでいうルード・セールスとして、得意先を定期的に回って注文を取る商法だ。しかも注文品を家まで運んでくれるのだから、便利この上ない。
当時、これはごく一般的におこなわれていて、若い店員の場合、「小僧さんが注文取りに来た」などと言われたりもしたものだ。コンビニはなく、通販も普及していなかったころのこと、この商いは広くおこなわれていた。
大城は連日、御用聞きに従事していた。注文を取るとそれを自転車で運んだ。味噌醤油からビール、日本酒 まで。荷台は数十キログラムの重さにたわみ筋肉は軋んだ。決して楽な仕事ではなかったが、体力に自信のあった若き大城は実直に取り組み、酒販店の売上げに大いに寄与していた。
ところで 御用聞きとは言い換えれば訪問販売のことではないのか。ちなみに消費者庁のホームページでは、「最も一般的な訪問販売は、消費者の住居をセールスマンが訪問して 契約を行うなどの販売方法です」と解説している。大城が日々、従事していた仕事は期せずして訪販そのものだったのだ。
そしてこの仕事は、後に大城が沖縄でソニー製品の販社を立ち上げたさい、日々実践した訪問販売の原点となった。それだけでなく、追ってネットワークビジネスとしてのエナジックビジネスを始めたさいにも、 訪販の経験は大いに役立ったと言えるだろう。
上京しメーカーに就職したが…
受注した品々の配達では高台の「屋敷町」へ行くこともある。重くなっ た自転車を力いっぱい押しながら「坂道でふと見上げると、りっぱな家が並んでいる。いつか僕もこんな住まいに……」。貧困にあえぐ中で、大城の上昇志向は強まった。 懸命に働きおよそ10カ月が経過すると、お金が多少貯まった。大城は「東京へ!」という念願を果たそうと、 酒販店の社長に率直に申し出た。「実 は学費を貯め東京で進学したいのです」と。社長は快く受け入れてくれた。
61年の春先。さっそく大城は上京した。しかし資金は足りず、結局、新宿区の京王線初台駅にほど近い金城電機商会という電話器関連の部品を製作する下請けメーカーに就職した。20歳になっていた。しばらくして、商業高校卒の経歴を買われ経理部へ。ここでは数字に強い大城の能力が十分に発揮された。給料の中から進学費用のための資金も少しずつ貯められるようになった。
こうしてようやく先のメドが立つかと思えた矢先、「父危篤」の連絡が入った。あわてて帰郷した。そして父の死を看取ると、そのまま生まれ故郷の久志村(現・名護市)に残ったのである。

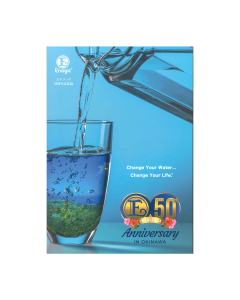
エナジック50周年記念誌に「半世紀の物語(全10話)」が掲載されています。
各支店またはエナジック オンラインショップ(EOS)からご購入いただけます。
販売価格:¥2,500(税込)